今回は一般的に家づくりに使われている屋根の種類と、それぞれのメリットデメリットについて詳しく解説します。
【種類1】和瓦(耐久年数40~50年)

古くからある屋根材です。
粘土を材料としており、伝統的な美しさと耐用年数がとても長いです。
日本瓦とも呼ばれている和瓦は、粘土を材料とした屋根材で、陶器瓦やいぶし瓦とも呼ばれます。
釉薬(うわぐすり)を使用し、表面でコーティングした瓦と無釉薬の素焼き瓦の2種類で分別されます。
次に和瓦のメリットについて解説します。
・メリット
耐久性が高い
和瓦のは、耐久性が他の屋根材と比較して高いです。
外的要因で瓦が割れてしまっても、一部の差し替えができます。
塗装によるメンテナンスが不要
スレート系のセメントが主成分の屋根材と違い、塗装の必要がありません。
なぜなら和瓦は陶器なので雨水が染み込むことによる劣化の心配がないからです。
例えば、大雨が降っていても、雨水による和瓦の劣化は心配する必要はありません。
通気性・断熱性・遮音性に優れている
瓦は、夏場の暑さを防ぎ、屋内を涼しく保つことができます。冬場は、外の冷気を遮断し、寒さを防げます。
理由は、瓦の素材自体の断熱性や構造上の空気層や通気性が優れているからです。
実際に、瓦は四季による気候変化の大きい日本の風土にあった屋根材で、古くから使われています。
雨音が聞こえにくいのも特徴です。
次に和瓦のデメリットについて解説します。
・デメリット
耐震性が低い
和瓦の重さは1m2あたり45~60kgの重さです。スレート屋根と比べて約2倍の重さがあります。
耐震性を考慮した場合、瓦屋根の重さはデメリットになるでしょう。
初期費用が高い
和瓦は、他の屋根材に比べ費用が高額です。
和瓦は、施工に専門的な知識や技術がいるため、施工費が他の屋根材よりも高くなります。
和瓦は塗装メンテナンスは必要ありませんが、瓦がずれた、瓦が割れた場合などは定期的な点検とメンテナンスは必要です。
瓦のずれ・割れ
ガイドライン工法(阪神淡路大震災を受け2001年に設定された地震や台風に強い瓦屋根の施工方法)で施工されていない瓦屋根のほとんどは、瓦桟と呼ばれ、屋根に載っている状態となっています。
そのため、地震や台風などの強風により瓦が剥がれ落ちる可能性があります。
定期的に専門業者に点検してもらい、必要があれば補修を行うと良いでしょう。
防水紙の劣化
瓦と板との間には防水紙があります。
防水紙は、屋根にとって重要な役割を果たします。
しかし、防水紙は、経年により劣化してしまいます。
実際に、非常に耐久性のある瓦ですが、瓦と瓦の間に隙間が生じるため、横殴りの雨などでは、他の屋根材に比べても雨水が瓦の下に侵入しやすくなります。
次にトタンについて解説します。
【種類2】トタン(耐久年数10~20年)
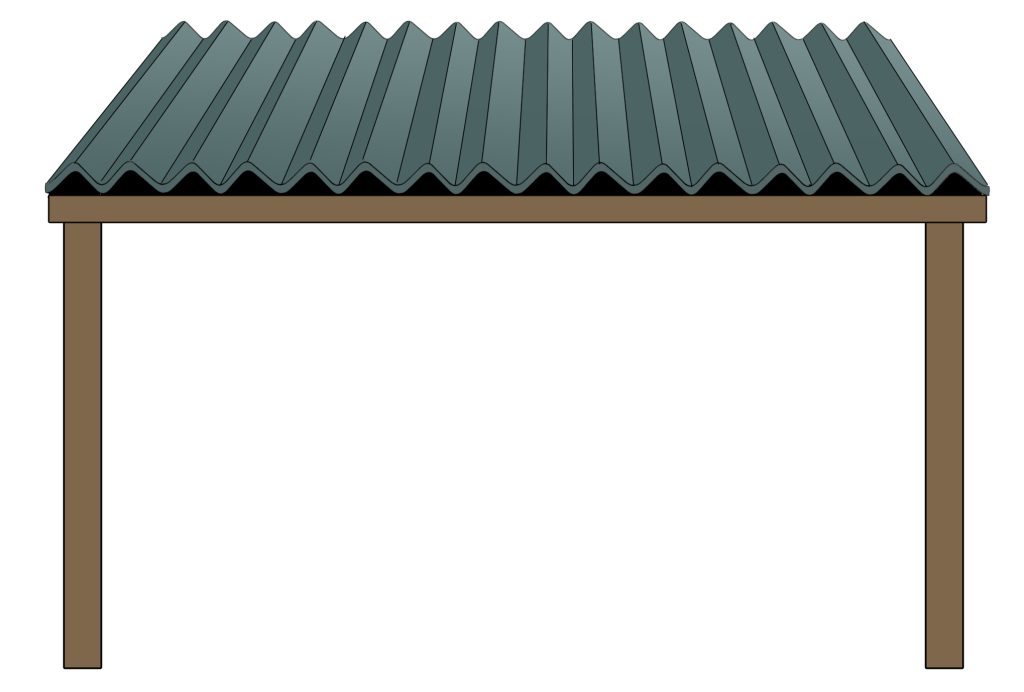
軽量で安価でありながら雨漏りしにくい屋根材です。
一昔前では多くの住宅の屋根や外壁で使われてきました。
トタンとは、薄い鉄板に亜鉛メッキを施した板状の金属材の一種です。
正式名称は、亜鉛鉄板・亜鉛引薄鉄板と呼ばれます。
トタン屋根とは、トタンを使用して作られた屋根のことで、住宅の他倉庫や工場にも使われています。
次にトタンのメリットについて解説します。
・メリット
費用が安い
トタン屋根の一番のメリットは他の屋根材に比べると費用が安いです。
材料費、人件費ともに抑えられます。
なぜなら、材料費が安く施工方法もシンプルだからです。
具体的には、補修や張り替えの際に材料費・施工費が安いのでコストが抑えられます。
屋根の勾配がゆるくても施工できる
トタン屋根は勾配がゆるやかな屋根形でも雨漏れの危険性が低いです。
理由は、基本的に一枚モノでの施工なので、継ぎ目が少ないからです。
実際、屋根材には雨水の流れを計算した上で、使用可能な勾配(屋根の傾斜角度)が決まっています。
勾配が緩い(角度が低い)と雨水がうまく流れずに、屋根材の隙間から漏水してしまう危険性があります。
耐震性に優れている
トタン屋根は耐震性に優れています。
なぜなら他の屋根材に比べてトタン屋根は非常に軽量だからです。
例えば、和瓦と比べると、重量は10分の1以下の重さで、非常に軽量です。
トタン屋根は、地震が来ても建物にも大きな負担がかかりません。
次にトタンのデメリットについて解説します。
・デメリット
メンテナンスしないと錆びる
トタンは、錆びてしまいます。
なぜなら表面の亜鉛メッキや塗膜などがコーティングされているからです。
実際に、劣化や傷がついてそこからサビが広がり、放置すると穴が空いてしまいます。
遮音性が低い
建物の構造にもよりますが、トタン屋根は雨が打ち付ける音が響きます。
理由は下地に直打ちしていることが原因です。
例えば、雨音が気になって眠れないケースもあります。
次にスレートについて解説します。
【種類3】スレート(耐久年数20~25年)
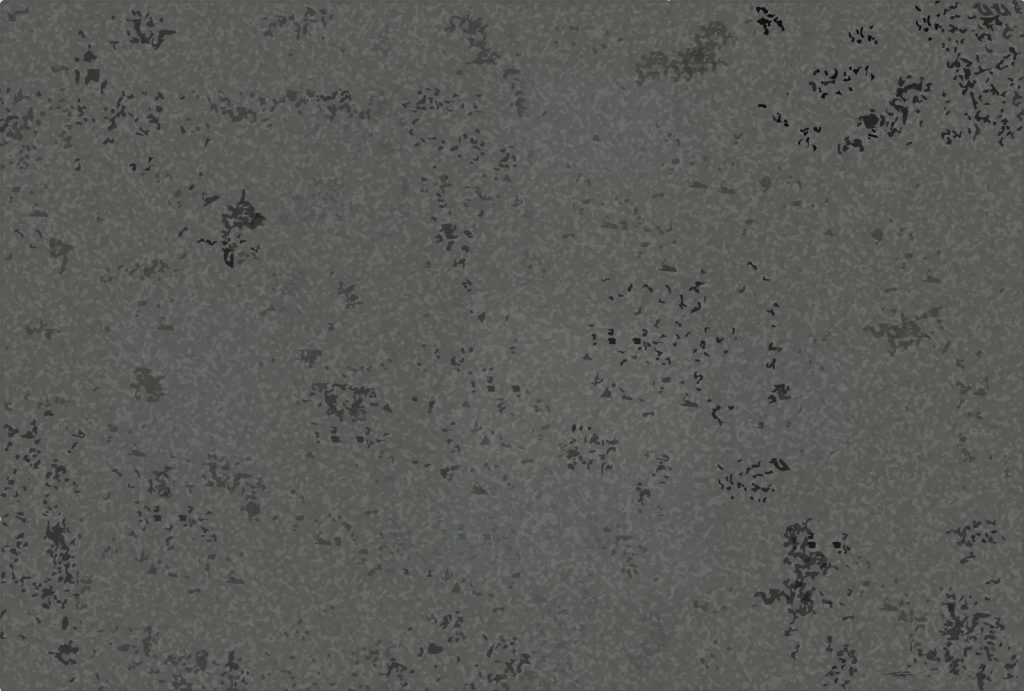
スレートとは粘板岩(ねんばんがん)を薄い板状に加工した建築材で、屋根材や外壁材として使用されます。
粘板岩を加工したものは天然スレートと呼ばれ、自然の風合いを生かした高級感のある素材です。
主に日本で普及しているのは、化粧スレートと呼ばれ、セメントに繊維素材を混ぜて薄い板状に加工したものです。
色やデザインが豊富で、材料費が比較的安価で施工も簡単で、現在の日本の新築住宅で最も多く使用されている屋根材です。
次にスレートのメリットについて解説します。
・メリット
価格が安い
スレートは現在日本の新築住宅で最も普及している屋根材です。
理由は、材料費が比較的安価であり、施工が容易だからです。
つまり、施工できる業者が多く、修理しやすくなります。
新築住宅で一番普及しているだけあり、施工できる業者、職人ともに多いです。
同じ理由で、点検、修理などに困ることがありません、一部の差し替えなどにも対応しやすいです。
重量が比較的軽い
一般的なスレートは、重量が粘土瓦の約半分です。
軽量な金属屋根材もありますが、重量級な屋根材に比べ軽いという点で耐震性に優れています。
地震が多い地域では瓦の重さから、瓦からスレートに葺き替えるところも多く見られます。
次にスレートのデメリットについて解説します。
・デメリット
割れやすい
他の屋根材に比べ割れやすいです。
なぜなら厚みが5mmほどだからです。
スレートが割れてしまうと雨漏れに繋がります。
具体的には、経年劣化により割れやクラック(ひび割れ)が発生しますが、施工の際も不用意に体重をかけると割れてしまいます。
屋根の種類とそれぞれのメリットデメリットまとめ
本記事では、屋根の種類とそれぞれのメリットデメリットについて解説しました。
和瓦(耐久年数40~50年)は、古くから日本で使われてきた伝統的な屋根材であり、粘土を主成分としています。
通気性・断熱性・遮音性にも優れていますが、耐震性が低く、初期費用が高いことがデメリットです。
トタン(耐久年数10~20年)は、軽量で安価な屋根材であり、一昔前では多くの住宅に使用されました。
亜鉛メッキを施した鉄板の一種であり、耐震性に優れていますが、メンテナンスを怠ると錆びや遮音性の低下が起こります。
スレート(耐久年数20~25年)は、粘板岩を加工した建築材で、色やデザインが豊富で価格が比較的安いため、日本の新築住宅で最も多く使用されています。軽量で施工も容易ですが、割れやすく、割れると雨漏りの原因になります。
栃木ハウスでは新築住宅に関する無料相談を実施しておりますので、興味のある方はお気軽に以下のフォームよりお申し込みください。
(作成スタッフ:姫野)
栃木・群馬・茨城・埼玉で家を建てるなら注文住宅の栃木ハウスへ


