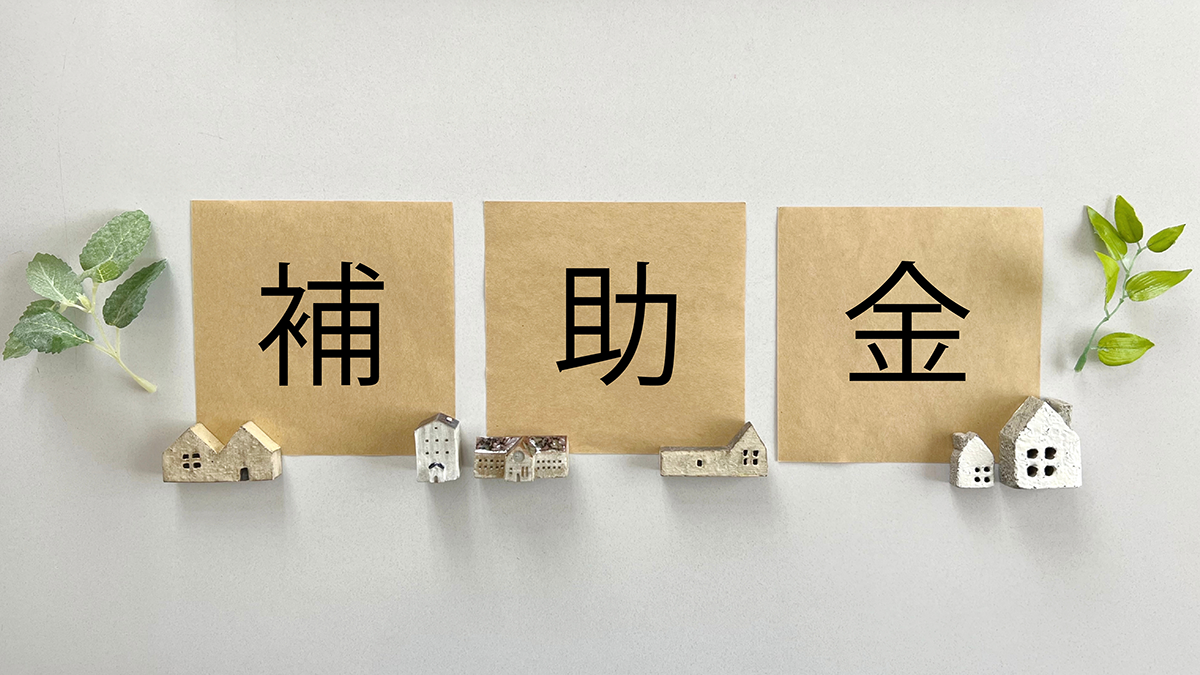「注文住宅を建てたいけれど、費用が心配…」「補助金を使えばどれくらいお得になるの?」そんな疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。近年は、省エネ性能の高い住宅を対象に国や自治体が支援を行っており、条件を満たせば数十万〜百万円規模の補助金を受け取れるチャンスがあります。ただし、制度の内容は年度ごとに変わるため、最新情報を正しく把握しておくことが大切です。
本記事では、2025年度の注文住宅向け補助金制度の概要と、2026年度に向けた動向、さらに補助金に頼らずコストを抑えるための実践的な節約術までをまとめました。栃木県で30年以上家づくりを行ってきた栃木ハウスの経験をもとに、賢く建てるためのポイントをわかりやすく解説します。
なぜ注文住宅は予算オーバーしやすい?3つの主な原因
注文住宅を建てた人の多くが、「思っていたよりも高くなった」と感じています。自由設計という魅力の裏側には、費用が膨らみやすい落とし穴が潜んでいるためです。家づくりは、建物価格だけでなく土地代・外構・諸費用など、さまざまな要素が重なって総費用となります。ここでは、予算オーバーを引き起こしやすい3つの代表的な原因を解説します。
「理想」の追求によるオプション追加
多くの人がやってしまうのが、「せっかくの注文住宅だから」と設備や素材にこだわりすぎてしまうケースです。キッチン・浴室・床材・サッシ・収納など、一つひとつのグレードアップは数万円〜数十万円単位ですが、積み重なると大きな額になります。
例えば、標準仕様のキッチンから標準外のシステムキッチンに変更するだけで+50万円、無垢床材を採用すれば+50万円といった具合です。さらに、設計変更が増えると追加設計料も発生するため注意が必要です。理想の家を追求することは大切ですが、最初に「優先順位」を明確にすることが重要です。“絶対に譲れない部分”と“妥協できる部分”を家族で話し合い、設計者と共有しておくことで、不要なコスト増を防げます。
見積もりに含まれない「付帯工事費」や「諸費用」
建物本体価格だけを見て契約してしまうと、後から「思わぬ費用が加算される」という落とし穴にはまりがちです。代表的な例として、地盤調査・外構工事・照明・カーテン・登記・引っ越し費用などが挙げられます。これらは見積もりに含まれないケースが多く、実際には建物価格の10〜15%が追加で必要になることもあります。
特に注意すべきは「付帯工事費」です。給排水の引き込みや電柱移設、造成工事などは土地の条件によって金額が大きく変わります。土地購入前に現地調査を行い、概算費用を把握しておくことで、資金計画のズレを最小限にできます。
地盤改良や予期せぬ追加工事の発生
土地の状態によっては、地盤改良工事が必要になる場合があります。改良費は50万〜100万円以上かかることもあり、契約時点では見積もりに含まれていないことがほとんどです。また、建築途中で設備や間取りを変更すると、材料費や施工費が追加されることもあります。
「あとから気づいた不便さ」を補うよりも、設計段階でしっかり検討しておく方が結果的にコストを抑えられます。
家づくりの費用については、「家を建てるには?費用や流れなど」の記事でも詳しく紹介しています。栃木ハウスでは、着工前に土地の地盤調査と仕様確認を徹底し、追加工事のリスクを最小限に抑えています。

【2025年】注文住宅で使える国の補助金制度を徹底解説
2025年度も、国は省エネ性能の高い住宅を推進するため、さまざまな補助金制度を整備しました。2026年度の制度は現時点(2025年10月)では未発表ですが、例年と同様にZEH水準住宅や長期優良住宅を対象とした支援が続く見込みです。ここでは、2025年に実施された主な国の補助金制度を詳しく見ていきましょう。
はじめに:住宅省エネ2025キャンペーンとは?
「住宅省エネ2025キャンペーン」は、国土交通省・経済産業省・環境省の3省が連携して実施している補助金制度です。省エネ住宅の普及を目的とし、注文住宅やリフォームを行う際に一定の性能基準を満たすと、補助金を受け取ることができます。制度は「子育てグリーン住宅支援事業」「給湯省エネ2025事業」「先進的窓リノベ2025事業」の3つに分かれています。
特に人気だったのは「子育てグリーン住宅支援事業」で、募集開始から数か月で予算上限に達するほど注目されました。
出典:住宅省エネ2025キャンペーン公式サイト(国土交通省)
子育てグリーン住宅支援事業
対象となる世帯と住宅の条件
子育て世帯(18歳未満の子どもがいる家庭)および若者夫婦世帯(いずれかが39歳以下)が対象。対象となる住宅は、省エネ性能が一定基準を満たす「長期優良住宅」または「ZEH水準住宅」です。建物の構造や断熱性能、設備の省エネ性が基準をクリアすることで補助金が適用されます。この制度により、省エネ住宅を建てる際の初期費用負担を軽減できるようになりました。
補助金額はいくら?長期優良住宅・ZEH水準住宅の違い
2025年度の補助金額は以下の通りです。
- GX志向型住宅:最大160万円
- 長期優良住宅:最大100万円
- ZEH水準住宅:最大60万円
補助対象となる住宅は、性能評価書などによって基準を満たしていることを証明する必要があります。また、子育て世帯や若者夫婦世帯には加算制度が設けられており、申請内容に応じて上限額が変わります。この制度は住宅ローン控除や自治体の助成制度とも併用できるケースがあるため、総合的に検討することが重要です。
2026年度も、国は引き続き住宅の省エネ化を後押しする方針を示しており、同様の補助金制度が設けられる可能性が高いと考えられます。
給湯省エネ2025事業
対象となる高効率給湯器と補助金額
家庭のエネルギー消費の中でも、給湯にかかるエネルギーは約3割を占めると言われています。その削減を目的として実施されたのが「給湯省エネ2025事業」です。対象となるのは、高効率な給湯設備を導入した新築住宅やリフォーム。
具体的には、以下のような設備が対象です。
- ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)
- ハイブリッド給湯器
- 家庭用燃料電池(エネファーム)
機器の種類に応じて、補助金は1台あたり10~20万円程度。ZEHやNearly ZEH住宅など、省エネ性能を高めた住宅との相性も良く、年間の光熱費削減効果も期待できます。2026年度も同様の省エネ給湯機器への支援が継続される見込みです。
先進的窓リノベ2025事業
新築でも対象になる?補助金の活用ポイント
窓や開口部の断熱改修を支援する「先進的窓リノベ事業」は、もともとリフォーム中心の制度でしたが、2025年度は新築住宅でも条件付きで対象になりました。樹脂サッシやトリプルガラスなど、高断熱仕様のサッシを採用することで補助が受けられます。
窓は熱損失の大きな部分であり、断熱性能を高めることで冷暖房費を年間約30%削減できるとされています。快適な室内環境を保つだけでなく、結露やカビの発生防止にもつながります。こうした補助金を上手に活用すれば、初期コストを抑えつつ快適で健康的な住まいを実現できます。
見逃し厳禁!お住まいの自治体独自の補助金・助成金
国の制度に加えて、都道府県や市区町村でも、住宅取得や省エネ設備の導入を支援する補助金制度が設けられている場合があります。たとえば、栃木県の「とちぎ住宅支援事業」や、各市町村のZEH補助金・移住促進支援などが代表的です。
これらの自治体独自の補助金は、地域の気候や人口施策に合わせて内容が異なり、年度ごとに更新されるのが一般的です。国の補助金と併用できるケースもあるため、建築予定地が決まった段階で、各自治体の公式サイトや住宅会社を通じて最新情報を確認しておくと安心です。
補助金申請のAtoZ!失敗しないための流れと4つの注意点

補助金制度は「知っているかどうか」で結果が大きく変わります。しかし、制度ごとに申請ルールが異なり、手続きのミスで受給できないケースも少なくありません。ここでは、補助金申請の流れと注意すべき4つのポイントを整理します。
基本的な申請の流れ(事業者申請がメイン)
補助金申請は、基本的に登録事業者である住宅会社や工務店が代理で行います。建築前に登録・申請が必要なものが多いため、「建てた後に申請できない」ことも。契約前に補助金を利用できるかどうかを確認しておくのが鉄則です。また、必要書類(設計図・性能証明書・領収書など)は住宅会社と施主双方で管理し、提出時期を逃さないよう注意しましょう。
注意点1:申請期間と予算上限を必ず確認する
補助金制度は年度ごとに予算が決まっており、上限に達すると早期終了します。たとえば2025年度の「子育てグリーン住宅支援事業」では、予算枠が想定を超えるスピードで消化されました。希望する補助金がある場合は、住宅会社と連携して早めに申請準備を進めることが大切です。
注意点2:補助金の重複利用は原則不可
同じ設備・工事に対して複数の補助金を併用することは原則できません。ただし、国の制度と自治体の制度を組み合わせるなど、対象が異なれば併用できるケースもあります。「どの制度が併用可能か」を見極めるためには、住宅会社が最新情報を把握しているかどうかが鍵になります。
注意点3:入居後の財産処分制限に注意
補助金を受けた住宅は、一定期間「自己居住」が義務づけられています。補助を受けてすぐに売却・賃貸に出すと、返還を求められる場合があります。ライフプランを見据え、長期的に居住する計画を立てておくことが大切です。
注意点4:対象となる住宅性能・仕様を契約前にチェック
補助金は「性能を満たすこと」が条件です。着工後の仕様変更で基準を満たさなくなった場合、補助金が受けられなくなるリスクがあります。契約時に「どの基準をクリアしているか」を書面で確認し、建築士や担当者と共通認識を持って進めましょう。
補助金だけじゃない!注文住宅のコストを賢く抑える5つの節約術
補助金を上手に活用することはもちろん大切ですが、それだけで全ての費用をカバーできるわけではありません。むしろ、「どのように家を設計し、どこにお金をかけるか」を工夫することで、結果的に数十万円〜数百万円の差が生まれます。
ここでは、住宅会社の現場で実際に取り入れられている、無理せずコストを抑えるための5つのポイントを紹介します。どれも「我慢」ではなく、「計画と工夫」で叶える節約術です。
建物の形状をシンプルにする(総二階など)
家の形は、見た目だけでなくコストにも大きく影響します。凹凸の多い外観や複雑な屋根形状は、その分だけ材料費と手間が増えるため、同じ床面積でも費用が上がります。一方、総二階のように1階と2階の形をそろえたシンプルな構造にすると、基礎や屋根の面積を最小限にでき、構造も安定。耐震性・断熱性の面でもメリットがあります。
また、外壁が直線的になることで施工精度も上がり、将来的なメンテナンス費も抑えられます。栃木県のように冬の寒暖差が大きい地域では、建物の形がシンプルなほど熱の逃げ道が少なく、冷暖房効率も高まります。外観デザインを工夫したい場合は、凹凸を増やすよりも「窓の配置」や「素材の使い分け」で表情をつけるのがおすすめです。
間取りを工夫して壁や廊下を減らす
廊下や壁が多い家は、その分だけ建材・施工費が増えるだけでなく、空間の使い勝手も悪くなりがちです。限られた面積の中で広く感じる家をつくるには、「動線を短く、空間を連続させる」ことがポイント。たとえば、リビング・ダイニング・キッチンを一体化したLDKや、廊下を極力減らす間取りを採用すれば、面積を効率的に使いながらコストも抑えられます。
また、仕切り壁を減らすことで冷暖房効率も向上し、長期的な光熱費の節約にもつながります。「広く感じるのに、無駄がない」家は、設計力の高い住宅会社ほど得意としています。
栃木ハウスでも、動線計画と収納配置を工夫することで、延床30坪前後でも開放感のある空間を実現した事例が多数あります。
キッチンや浴室など水回りの設備を集中させる
家づくりの中で見落としがちなのが、水回りの配置計画です。キッチン・浴室・洗面所・トイレなどをバラバラに配置すると、その分だけ給排水管や給湯管が長くなり、配管コストが上がります。
反対に、水回りを1か所にまとめると配管が短くなり、施工費を10〜20万円程度抑えられるケースも珍しくありません。また、配管距離が短いと水圧の低下や熱損失も少なく、光熱費面でもメリットがあります。2階に水回りを設ける場合は、上下で位置を合わせることでさらに効率化できます。
「暮らしやすさ」と「コスト削減」を両立させるポイントは、建物全体を俯瞰して設備を集約設計すること。設計士と早い段階から相談すれば、生活動線を損なわずに無駄のないレイアウトが実現できます。
設備のグレードにメリハリをつける
注文住宅では、キッチン・浴室・トイレ・照明・建具などを自由に選べるため、つい上位モデルを選びたくなるもの。しかし、全てを高級仕様にすると予算が一気に膨らみます。そのため、よく使う場所・長く目にする場所に重点的に予算を配分し、使用頻度の低い部分は標準仕様を選ぶのが賢い選択です。
たとえば、キッチンは毎日使うため清掃性や収納性を重視し、トイレや洗面台はシンプルな仕様に。床材も、リビングは無垢材や突板フローリングで温かみを出し、2階の寝室や廊下は量産フロアを選ぶなど、空間ごとにバランスを取る方法があります。この「メリハリ設計」を実践するだけで、総額で50〜100万円の差が出ることもあります。
また、標準仕様の中にもデザイン性の高いメーカー製品が増えており、コストを抑えつつ上質な空間をつくることが可能です。
外構工事は後から分離発注も検討する
外構(エクステリア)は、家づくりの中で後回しにされがちな部分ですが、意外と大きな費用がかかります。駐車場のコンクリート打設、フェンス、ウッドデッキ、門柱、植栽などを一式で依頼すると、100万〜300万円程度になることもあります。そのため、建物引き渡し後に専門業者へ直接依頼する「分離発注」を検討するのもひとつの方法です。
実際、分離発注にすることで中間マージンを抑え、同じ仕様で20〜30万円ほど節約できた事例もあります。ただし、基礎や排水など建物と関係する部分は同時施工が原則。構造に関わらない装飾的な部分(花壇・フェンス・照明など)を後から追加する形が理想的です。
また、すぐに全てを完成させず、必要最低限の部分だけ先に整え、将来的にDIYやリフォームで手を加えていくという考え方もあります。「家とともに成長する外構」は、コストを抑えながらも愛着を育てる方法のひとつです。
まとめ:補助金と節約術を賢く利用して、予算内で理想のマイホームを実現しよう

注文住宅は、自由度が高い分だけ費用が膨らみやすく、予算オーバーになってしまう人も少なくありません。しかし、国や自治体の補助金制度を上手に活用し、設計や仕様の工夫を重ねることで、無理のない資金計画の中で理想の住まいを実現することができます。
2025年は、子育てグリーン住宅支援事業をはじめとした「住宅省エネキャンペーン」によって、省エネ性能の高い注文住宅への支援が充実しました。2026年度も、環境負荷を減らす高性能住宅への補助制度が継続される見込みです。補助金を上手に活用することで、初期費用を抑えながら快適で光熱費の少ない住まいを手に入れることができるでしょう。
一方で、補助金は申請時期や対象条件を誤ると受給できない場合もあります。「申請は施工会社に任せきり」ではなく、施主自身も制度の概要を理解しておくことが安心です。信頼できる住宅会社と二人三脚で、最新情報を確認しながら進めるのが最も確実な方法です。
また、補助金だけでなく「設計段階での工夫」や「建物形状・設備の選び方」も大切なポイント。例えば、総二階のシンプルな構造にする、間取りを効率化する、水回りを集中させるなど、工夫次第で100万円単位のコスト削減が可能です。高性能な住宅ほど、建築後の光熱費・メンテナンス費用も減らせるため、“建てた後のコストまで含めた長期的な視点”で資金計画を立てることが理想的です。
栃木ハウスでは、創業以来30年以上にわたり、栃木県内の気候・土地条件を熟知した家づくりを行ってきました。補助金制度を最大限に活用しながら、地域特性に合った高断熱・高耐久の注文住宅をご提案しています。「予算の中で理想の家を叶えたい」「補助金を上手に使いたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富なスタッフが、資金計画から設計・施工・アフターサポートまで、一貫してお手伝いします。モデルハウス見学予約や無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
栃木・群馬・茨城・埼玉で家を建てるなら注文住宅の栃木ハウスへ